
きのう3月29日は、千里中央で「せんりひとつなぎフェス」がありました。豊中市が音頭をとり、せんちゅうパルも連携して、市の施設であるコラボの館内や、つづきの空間になっているせんちゅうパル北広場で、市民グループや商業者の皆さんがテーブルやテントを出して「商民一体の」ちょっとしたお祭りと言ったらいいんでしょうか。春の日ざしに恵まれて楽しい空間が演出されていました。マチカネくんの姿も見えますね。
ふだんは通路になっているコラボ多目的室前のテラスにもテーブルが出ています。ワークショップを何度も重ねて、「これから千里」で何をしたいか?どこをどのように使いたいか?アイデアを出し合った最終発表会のイベントがこの日…というしつらえ。プロセスに念が入っています!
こういうシーンは千里ではとくに珍しくもないですが、思い出したのは「千里ニュータウンは欧米式の『広場のにぎわい』を中心に設計されている」というS先生のお言葉。日本の町のにぎわいは、古来「通り」を中心に発達してきて、そういったシーンは大河ドラマ「べらぼう」でも出てきます。吉原で仕掛けられたお祭りは「通り」で行われていて、公園や広場ではやっていません。
しかし日本のニュータウンは…千里を筆頭に、欧米式の「広場」をにぎわいの空間として設計されている。今は廃墟になっているセルシー広場が千里では有名ですが、セルシーだけじゃないのです。
千里の古い写真を集めている「北摂アーカイブス千里丘陵コレクション」では、54年前のほぼ同じ場所の写真も見られます。背後の建物はすっかり変わっていますが、「広場の楽しみ方」は受け継がれていますね。
こういった千里ニュータウンの設計のキーパーソンになったのは京大の西山夘三氏で、氏は千里の万博会場の「お祭り広場」の設計を実現させた人でもあります。欧米的な概念の「広場」に、日本的な「お祭り」を組み合わせてしまったのは、すごい仕掛けです。千里ニュータウンと万博はお隣りですが、同じキーパーソンにつながっていたことを考えると、この千里中央の広場も、万博の「お祭り広場」の仲間と言えるのでしょう。その「使いこなし」を、千里の人たちはなんとなくわかってしまっているのですね。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。



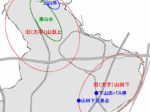


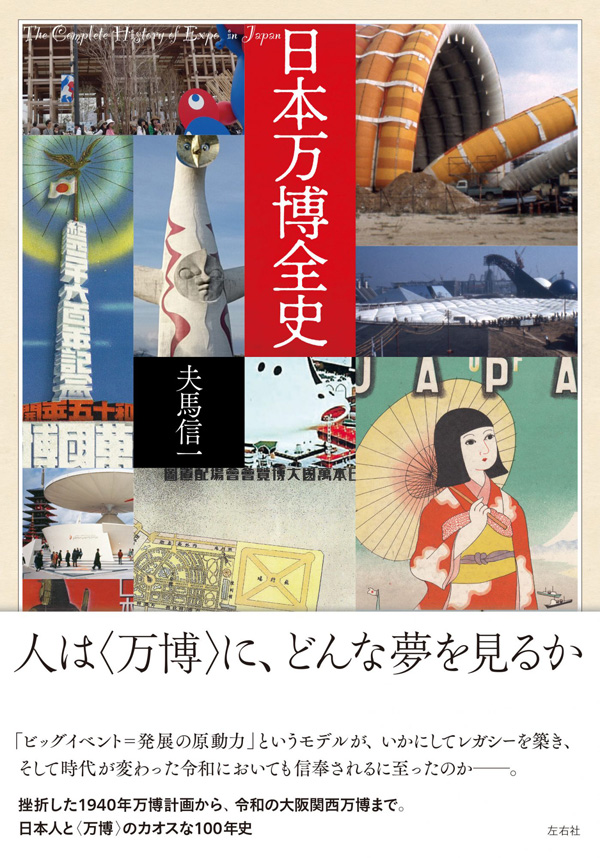
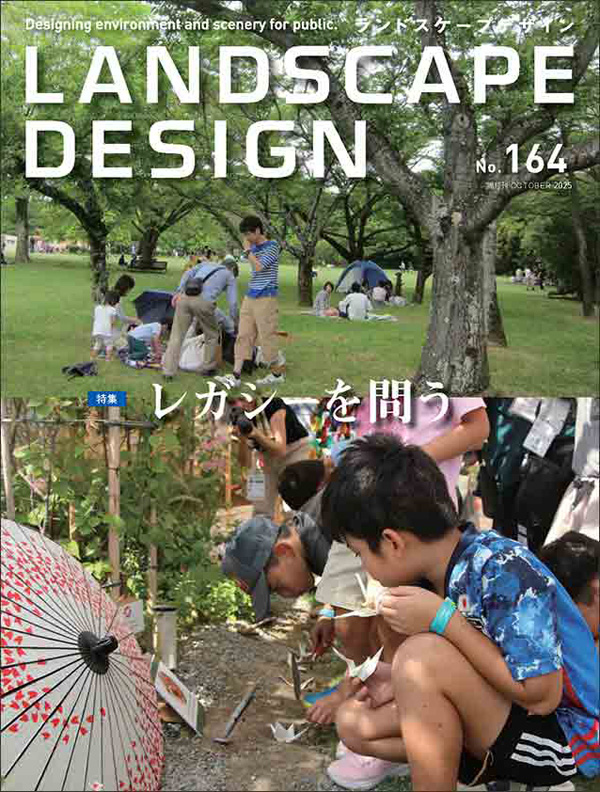 ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。
ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。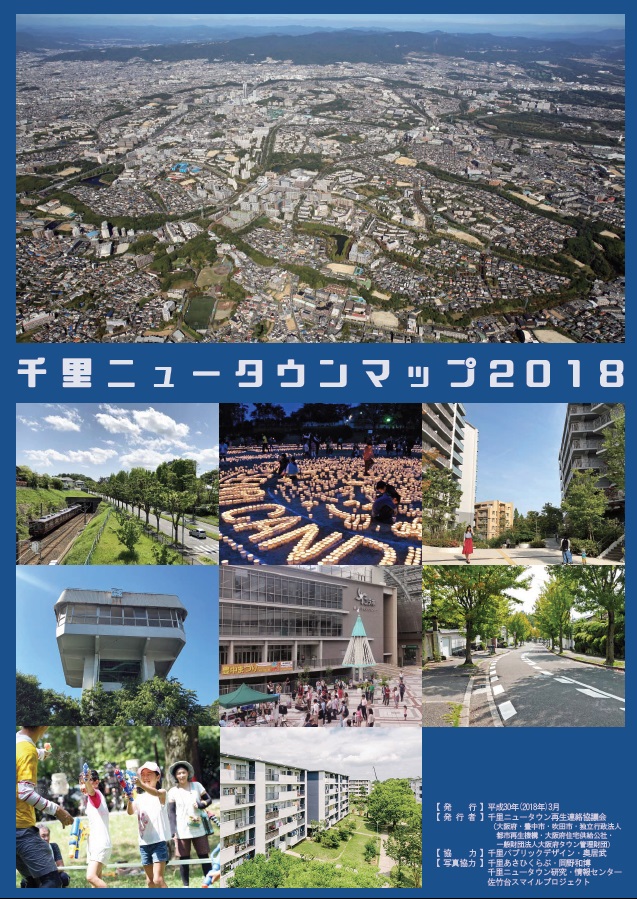

この記事へのコメントはありません。